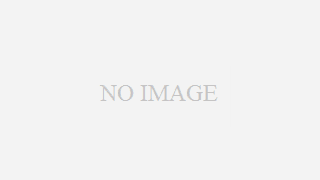 乳がんの治療について
乳がんの治療について 乳がん 化学療法 薬物療法に関する情報
乳がん 化学療法 薬物療法に関する情報をまとめています。乳がん 化学療法抗がん剤治療という言葉から連想される、最も一般的な治療法がこの化学療法です。抗がん剤は乳がんの広がりに対して、術前化学療法、術後化学療法、そして遠隔転移に対する化学療法...
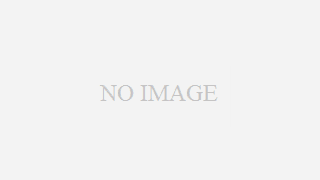 乳がんの治療について
乳がんの治療について 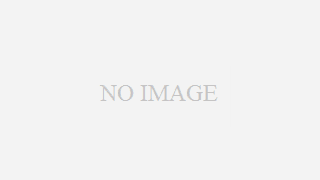 乳がんの治療について
乳がんの治療について 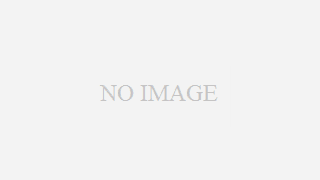 乳がんの治療について
乳がんの治療について