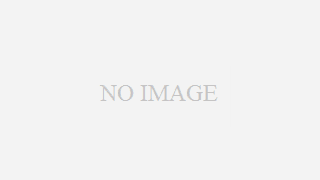 乳がん検診と症状
乳がん検診と症状 乳がん検診の重要さ
生存率は検診で乳がんが見つかった人のほうが高い現代は、2人に1人が何らかのがんになってもおかしくない時代ですから、がん検診を受けることが必要なのは、みんなわかっていると思います。それなのに、日本では女性の検診受診率がとても低いのが現実です。...
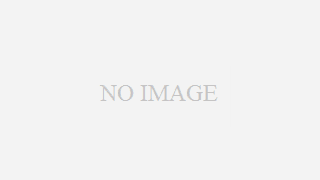 乳がん検診と症状
乳がん検診と症状 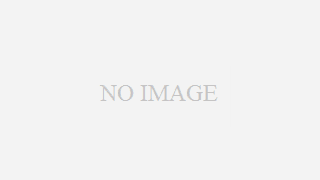 知りたい!乳がんのこと
知りたい!乳がんのこと 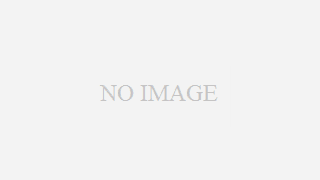 知りたい!乳がんのこと
知りたい!乳がんのこと