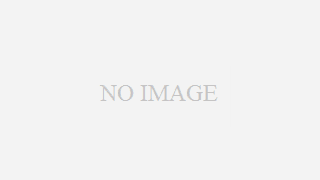 乳がん治療のための検査
乳がん治療のための検査 センチネルリンパ節生検
乳がんは治療法の進歩により、世界的に患者の生存率が向上しています。現在では、乳がんの手術にセンチネルリンパ節生検は標準的な検査法です。リンパ節への転移があるかないかを調べる検査法がん細胞が、がん巣から離れてリンパ液の流れにのってリンパ節まで...
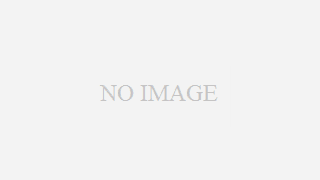 乳がん治療のための検査
乳がん治療のための検査 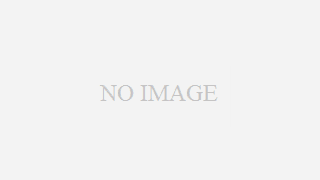 乳がん治療のための検査
乳がん治療のための検査 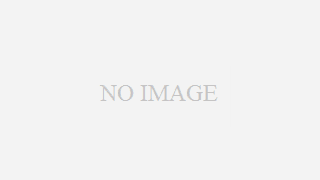 乳がん治療のための検査
乳がん治療のための検査