ガン患者さんは お酒 適量 を守る ビールならジョッキ2杯までが基本です。お酒との付き合い方は、ガンを防ぐ食習慣の中でもとても大切です。「適量」という言葉はよく耳にしますが、がんを患っている方にとっての「適量」は、健康な方のそれとは大きく異なる場合が多いです。
お酒 適量 ビールならジョッキ2杯まで
また、一般的に言われる「ビールならジョッキ2杯まで」という目安も、がん患者さんにとっては当てはまらない可能性があります。
アルコールについては、数ある飲食物の中で、がん発生との関連がもっともはっきりしているのが、お酒です。
よく「酒は百薬の長」といわれます。適量の飲酒は血行を促進する、心身をリラックスさせる、気分を朗らかにするなど、健康増進に役立つと考えられています。
がんとの関連でも、少量の飲酒をする人はまったく飲まない人に比べて、がんの発症が少ないというデータもあります。しかし、アルコールのよい効果を期待できるのは、あくまでも適量を守った場合です。
摂取量が多くなると、今度は害のほうが大きくなります。国立がん研究センターの研究によると、日本人男性では、1日の飲酒量が日本酒換算で2合を超えるとがんの発生率が高くなると指摘されています。
アルコールを「時々飲む」人のがん発生率を1として、1日の飲酒量が2合以上3合未満の人は発生率が1.41倍、3合以上になると1.61倍になります。飲酒量が多くなるほど、がんの発生率が上がるという相関関係になっています。
アルコールが原因でかかりやすくなるがんは、喉頭がんや咽頭がん、食道がんなどが挙げられます。これらのがんが増えるのは、飲んだアルコールがのどや食道を通過する際に、粘膜を傷つけるためと考えられています。お酒といえば肝臓がんと連想する人も多いと思いますが、ご想像のとおり、アルコール分解にかかわる臓器の肝臓がんも、飲酒によって増加します。
大腸がん、乳がんも飲酒と関連が深いがんですが、これにはアルコールが分解ざれる過程でできる発がん物質のアセトアルデヒドが影響しているといわれています。
それでは、適量とはどのような量を指すのでしょうか。厚生労働省が示す飲酒の適量の目安は、純アルコール量にして約20gです。よく飲むお酒の種類ごとに、適量に相当する量を知っておくと便利です。たとえば日本酒や焼酎(25度)では1合( 約180ml)、ビールはジョッキ2杯(約600ml )、ワインならグラス2杯(約200ml)です。
これは1 種類のアルコールでの適量ですから、飲み会などでビールをジョッキ2杯飲んで、その後に日本酒を1合飲んだとなると、もうそれで2日分の飲酒量になってしまいます。
いったん飲み始めると適量ではなかなか収まらないという人は、翌日、翌々日に休肝日を設けるなどして飲酒量を3日間1セットとして調整することが大切です。
アルコールの分解能力は人によって個人差が大きいものです。お酒を飲むとすぐに顔が赤くなる人は、そうでない人に比べてがんのリスクが高くなります。
「適量までならいいだろう」と油断せず、飲酒量を控えめにしたほうが安心です。また女性も男性に比べると肝臓が小さく、アルコールの分解能力も低い傾向があります。
お酒で顔が赤くなる人と同様、過度の飲酒にはより注意が必要です。また量を守って飲むなら、どの種類のアルコールがいいかという質問も、よく耳にします。アルコールの種類とがん発生については、今のところはっきりとした関係はわかっていませんが、食道がんや咽頭がんなどはアルコール度数が高いものを長期間飲酒しているとなりやすいといわれています。
肥満や糖尿病などの生活習慣病の面からいえば、最近は糖質を含まないアルコールが注目されています。ビールや日本酒などの醸造酒は糖質を比較的多く含むため、飲酒後に血糖値が多少上昇します。
一方、焼酎やウィスキーなどの蒸留酒は糖質を含まないため、血糖値を上げません。また、辛口のワインは糖質も含有量が少ないため、体重増にはつながりにくいとされていますので、ストレスをためながら無理に禁酒する必要はありません。
もともと「お酒は太る」というイメージがありますが、お酒のカロリーは「エンプティーカロリー(カロリーの少ないもの)」と呼ばれているぐらいで、体内で速やかに消費され、蓄積されにくいのです。
ダイエットの際に注意しないといけないのはお酒でなくて、むしろお酒と一緒に食べるおつまみなのです。糖質や脂肪分の多いおつまみは避けるように心がけてください。
おすすめは、アボカドやズッキーニなどの糖質の少ない食材を使ったおつまみです。ズッキーニを生ハムで巻いたり、スモークサーモンにアボカドを添えた料理など、工夫をすれば簡単でおいしいおつまみがたくさんありますので、ぜひおすすめします。
最近は「糖質ゼロ」をうたったビールや日本酒も商品化されていますので、血糖値や体重の増加が気になる人はこうした製品や、蒸留酒を選ぶといいでしょう。
ひとつ注意したいのは、焼酎やウィスキーは水割り、ソーダ割りなどで濃度を薄くして飲むのがよいということです。アルコール度数の高い強いお酒を水やソーダで割らずにそのまま飲むと、食道などの粘膜に傷がつきやすくなり、発がんのリスクが高まります。
ただ、どんな種類のアルコールにしても、飲み過ぎはがん体質をつくり出します。アルコールとは「ほどはど」の付き合いを心がけるようにしてください。
「適量」の認識とその落とし穴
健康な成人における一般的な「適量」の目安は、厚生労働省の「健康日本21」などで示されており、純アルコール量で1日あたり約20g程度とされています。これは、ビール大瓶1本(500ml)、日本酒1合(180ml)、ワイングラス2杯弱(200ml)、焼酎(25度)0.6合(120ml)などに相当します。ビールジョッキ2杯は、銘柄やジョッキのサイズにもよりますが、大瓶1本分をやや超えるくらいのアルコール量になることが多いでしょう。
しかし、この「適量」はがん予防や一般的な健康維持のための目安であり、がん治療中の方や、特定のがんの種類、既往歴のある方には適用されません。
がん患者さんが飲酒を控えるべき理由
- 治療への影響:
- 薬剤との相互作用: 抗がん剤や他の薬の代謝に影響を与え、効果を弱めたり、副作用を強くしたりする可能性があります。
- 副作用の悪化: 吐き気、下痢、口内炎などの副作用をアルコールが悪化させる可能性があります。
- 肝臓への負担: 多くの薬剤が肝臓で代謝されるため、アルコールは肝臓にさらなる負担をかけます。
- 再発・新規がんのリスク:
- アルコール自体に発がん性があり、がんの発生リスクを高めることが明らかになっています。治療後であっても、飲酒はがんの再発リスクを高めたり、新たながんを発生させるリスクを高めたりすることが指摘されています。特に、口腔、咽頭、喉頭、食道、肝臓、大腸、乳房など、アルコールとの関連が強いがんがあります。
- 体力低下と免疫力:
- 治療で体力が落ちている時にアルコールを摂取すると、さらに体力を消耗し、免疫力の低下につながる可能性があります。
- 栄養状態の悪化:
- アルコールは、食欲不振を引き起こしたり、栄養の吸収を妨げたりすることがあり、治療に必要な栄養状態の維持を困難にする場合があります。
がん患者さんにおける飲酒の最終判断
繰り返しになりますが、がんを患っている方にとっての飲酒の可否、そしてその「適量」は、個々の病状、治療内容、使用している薬剤、経過、そして医師の判断によって大きく異なります。
「ビールならジョッキ2杯まで」という一般的な目安は、がん患者さんには当てはまらない可能性が高いと認識してください。

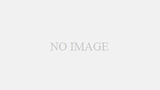
コメント
[…] お酒は飲み過ぎてはいけないし、ガンのリスクになります。 お酒は適量を守る ビールならジョッキ2杯まで […]